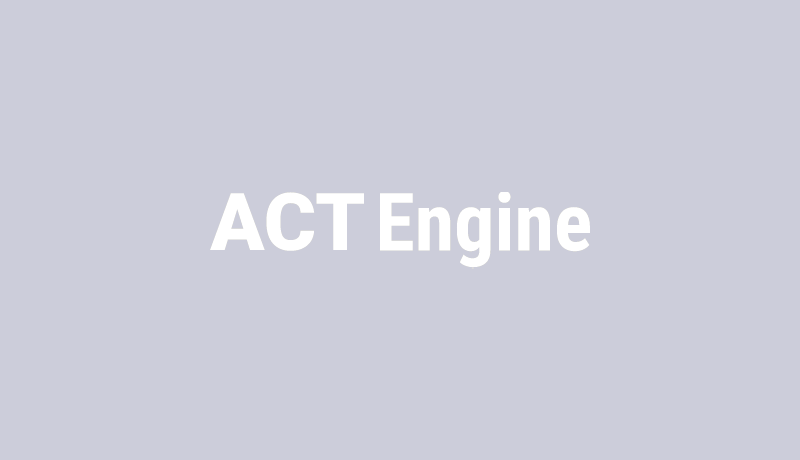【やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ】
とは、旧日本海軍の連合艦隊司令長官であった、山本五十六 の有名な言葉の一つです。
ちなみにこれには続きがあって、
【話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず】
【やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず】
こうやってみると戦時中で統率力はかなり強かったと思える日本軍であっても、人を育成するのは組織の課題であり、上に立つ者はいつも頭を悩ましていたということが見て取れます。
ですが、これらの言葉は今でも十分通用する金言で、どんな時代であっても、人は人ということが良く分かる言葉でもあります。
このコラムをご覧になる方は建設関係の方が多いと思いますが、施工管理のお仕事などをされている方は、特にこれらの言葉は考えさせられるものじゃないでしょうか?
ただ、これらの言葉に共通して言えるのは【相手に敬意を払わないと人は動いてはくれない】ということ。
人の上に立つと役職名で人が動いてくれると勘違いする人もいますが、もちろんそれだけでは人は動いてくれません。
人はこの人のためなら動こうという意思が少しでもないと動いてくれないものなのです。
もちろん命令という名のもとに強制しても良い結果は出ません。
良い結果を生むためには自発的行動を促す必要があります。
その自発的行動を起こすためには、山本五十六の言葉にもあるように、まずは上に立つ者が率先して範を示す必要があるわけです。
ちなみに海上自衛隊幹部候補生学校には、旧日本海軍から伝わる【五省(ごせい)】という五つの訓戒があります。
一、至誠に悖る勿かりしか
※真心に反する点はなかったか
一、言行に恥づる勿かりしか
※言動に恥ずかしい点はなかったか
一、氣力に缺くる勿かりしか
※精神力は十分であったか
一、努力に憾み勿かりしか
※十分に努力したか
一、不精に亘る勿なかりしか
※最後まで十分に取り組んだか
幹部として、人の上に立つ者として、毎日1日の終わりに発唱し、自らの1日の行いを反省するそうです。
人を動かす立場になって悩む方は多いと思いますが、そんな時にこんな言葉を思い出しながら、自分の行動や発言を顧みて、「相手への敬意が十分であったか?」「自分が範を示すことができれいるか?」と確認して行く作業をしてみてはいかがでしょうか?
少し何か見えてくるものがあるかもしれません。
もし良かったら実践してみてはいかがでしょうか?